新着情報
安くて簡単”の裏にある落とし穴?直葬を選ぶ前に知っておきたい5つのポイント

Contents
「直葬(ちょくそう)」という言葉を耳にすることが増えた今、費用が抑えられ、シンプルに見送れる方法として注目されています。
しかし、現場で多くのご家族と接してきた私たちの経験から言えるのは、直葬は“安くて簡単”というイメージだけで決めてしまうと、後から悩みや後悔につながることがあるということ。
この記事では、直葬を検討している方に向けて、実際の現場で見た“リアル”な事例を交えながら、選ぶ前に知っておいてほしい5つのポイントを丁寧に解説します。
-
はじめに:直葬が増えている背景と、いま考えておきたいこと
近年、「直葬(ちょくそう)」という形を選ばれる方が増えています。
通夜や告別式といった儀式を省き、火葬のみを行うシンプルなスタイルは、「費用が抑えられる」「時間的な負担が少ない」といった理由から注目されるようになりました。特に高齢化や核家族化が進む中で、「なるべく負担をかけずに見送りたい」という思いを持つご家族にとって、直葬は現実的な選択肢の一つとなっています。
しかし、私たち葬儀社の立場から見ると、「本当にそれでよかったのか…」と、後から悩まれる方も少なくありません。
直葬は決して“簡単に済ませる”だけの方法ではなく、ご家族や親族との関係、宗教や地域の慣習、さらには今後の人間関係にも影響を及ぼす可能性がある、非常に繊細な選択です。
この記事では、現場で直葬に立ち会ってきた私たちだからこそ伝えられる、直葬の実態や注意点についてご紹介します。
「直葬で本当にいいのか?」と迷っている方が、ご自身にとって納得のいく判断をするための材料として、少しでもお役に立てれば幸いです。
✅直葬とは?基本の流れを簡単に
直葬とは、通夜や告別式などの儀式を行わず、火葬のみで故人を見送る葬儀の形です。病院などで亡くなられた後、ご遺体は自宅や安置施設に搬送・安置され、火葬の日時が決まるまでは静かに過ごすことになります。
特に都心部では、自宅での安置が難しいケースも多く、火葬場に併設された霊安室を利用する方が一般的です。霊安室に預ける場合は、利用時間や費用の確認も事前に必要となります。
火葬当日は、火葬場に移動し、ご家族との対面やお花入れなど、簡単なお別れの時間を設けてから火葬へと進みます。お別れの時間は火葬場にもよりますが、多くの場合は5〜10分程度と限られています。「しっかりお別れをしたかった」と感じる方も少なくないため、事前に流れや時間感覚を知っておくことはとても大切です。
直葬が選ばれる背景としては、「高齢で付き合いが少なかった」「故人の遺志で葬儀を望まなかった」「経済的な理由」などが挙げられますが、その背景はご家族それぞれ異なります。流れが簡素であるからこそ、必要な準備や注意点を理解し、納得のいく形に整えることが求められます。
以下の図は、直葬(火葬式)の基本的な流れを9つのステップで示したものです:
-
臨終 – ご家族に看取られ、医師が死亡を確認。

-
搬送 – ご遺体を病院から寝台車で搬送。

-
安置 – 斎場や火葬場などの安置施設へご遺体を安置。
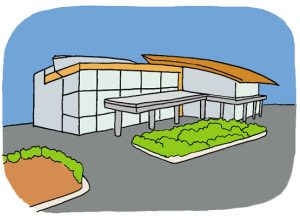
-
打ち合わせ – 葬儀社との打ち合わせ。費用や日程を確認。

-
薄化粧 – ご遺体へのメイク、身支度の整え。

-
納棺 – 副葬品(可燃物)や花を棺に納める。

-
お別れ – 顔を見て最後のお別れ

-
火葬場 – 火葬(約1時間から1時間30分)※火葬時間は火葬場により異なる

-
骨あげ – あいばさみで骨を骨壺へ。解散。

✅実際にあったケースから見る、直葬のメリット・デメリット
直葬は、シンプルで費用も抑えられる一方で、実際に経験された方々からは「やってよかった」という声と「もう少し考えればよかった」という声の両方を耳にします。ここでは、実際の現場で見たご家族の例をもとに、メリットとデメリットの両面をお伝えします。
【ケース1】「やってよかった」:高齢の母の希望を尊重して
90代のお母様を見送られたご家族は、「生前から『静かに、簡単でいいからね』と言っていた」というご本人の意向を尊重して直葬を選ばれました。お別れの時間は限られていましたが、火葬前にお花を手向け、静かに手を合わせることができ、「母らしい最期だった」と心穏やかに見送ることができたと話されていました。
【ケース2】「少し後悔」:本人の意志を尊重したが…悩ましかったケース
現役世代のサラリーマンだった方が闘病の末に亡くなられ、ご家族は「本人が直葬でいいと言っていたから」と直葬を選ばれました。
葬儀社側としては、年齢や立場を考えると、職場や友人など多くの方が「お別れの場を望んでいるのでは」と感じましたが、費用を上乗せしたいように見られてしまう懸念や、依頼を断られたらという不安から、強くはアドバイスできませんでした。
結果的に直葬は無事に終わりましたが、後日奥様から「もしかすると、いろんな方に来てもらったほうがよかったのかもしれない」と話がありました。遺族としては納得しているものの、どこか心に引っかかるものが残っていたようでした。
【ケース3】「思わぬトラブル」:菩提寺との相談を怠った
以前、他の葬儀社で直葬を行った方から伺ったお話です。
火葬後に菩提寺へ納骨の相談をしたところ、「なぜ事前に相談しなかったのか」とお寺からお叱りを受けてしまったそうです。
信頼できる葬儀社であれば、菩提寺がある場合は、葬儀の形式や日程を決める前にご遺族から必ず連絡を入れてもらうようアドバイスします。
このひと手間を怠ると、最悪の場合、納骨を断られることもあるからです。
その後、改めてお骨の状態で葬儀を行う「骨葬(こつそう)」を本堂で執り行うことになったそうです。事前にお寺とよく相談しておけば、こうした行き違いは避けられたかもしれません。

最近では、特に都心部では直葬が広く受け入れられつつあり、親戚からの強い反対は減ってきています。しかし、菩提寺や近しい人々との関係性、そして「葬儀が担う心の区切り」という役割をどう捉えるかによって、満足度は大きく左右されます。
現場で多くのご家族を見送ってきた立場から言えるのは、「形式よりも、“何を大切にするか”を事前に家族で話し合うこと」が、最も後悔のない選択につながるということです。
✅ 直葬にかかる費用と、その内訳の実情
直葬は「費用が安い」として注目されることが多い葬送形式ですが、実際にかかる費用の内訳や注意点を正しく理解しておくことが大切です。
相場としてよく目にする15万〜25万円程度という金額は、「基本プラン」の料金であり、これには葬儀社が提供する最低限のサービスが含まれます。
しかし実際の総費用としては、火葬場に支払う費用やオプション料金が別途必要になるため、費用の内訳は大きく3つに分けて考えることが重要です。
■ ①基本プラン費用(葬儀社に支払うパッケージ料金)
この中には主に以下の内容が含まれます:
- 寝台車によるご遺体の搬送(病院〜火葬場霊安室)
- 安置料(1日分)
- 棺
- ドライアイス(1日分)
- 死亡届の提出代行
- 人件費(打ち合わせ、納棺、火葬当日のご案内)
■ ②火葬場に支払う実費(現金払い)
- 火葬料金(自治体により無料〜数万円)
- 待合室や控室の使用料
- 骨壺代(火葬場で直接支払う地域も)
これらは葬儀社の費用とは別に、当日現金で支払うケースが多いため、事前に確認が必要です。
■ ③オプション費用(希望によって追加)
- お別れ用の生花(花入れ)
- 遺影写真
- エンゼルメイク
- 安置期間が延びた場合の追加料金
- 棺や骨壺のグレードアップ など
- 寝台車によるご遺体の搬送(ご自宅や安置所〜火葬場)
また、「行政手続き代行」と記載されている場合でも、葬儀社が対応できるのは死亡届の提出のみです。
年金・健康保険・相続などの各種手続きは、ご遺族ご自身で行う必要があります。
最近では、市区町村によっては「お悔やみコーナー」や「おくやみ窓口」といった相談窓口を設けており、ひとつの窓口で複数の手続きに対応できるワンストップサービスを利用できるケースも増えています。こうした公的サポートも活用しながら、スムーズな手続きを進めていくことが大切です。
「安さ」で直葬を選ぶのはもちろん悪いことではありませんが、必要な項目や希望に応じて費用が加算される場合もあるため、全体の費用構成を正しく理解しておくことが、後悔しない選択につながります。
✅ 後悔しないために考えておくべきこと
直葬は確かにシンプルで、費用も抑えられる合理的な選択肢のひとつですが、「あとになってから後悔する」ケースがあるのも事実です。多くのご家族と向き合ってきた中で見えてきたのは、費用や流れだけでなく、“人との関係性”や“気持ちの整理”をどうするかが重要だということです。
まず、親族や親しい知人への事前説明については慎重な判断が求められます。亡くなったことを知らせたことで、火葬当日に多くの人が駆けつけ、結果的に直葬では対応しきれなくなることもあります。「本人の意向だから静かに見送ってあげたい」と思っていても、周囲の反応によっては直葬を断念せざるを得ないケースもあるため、誰に・いつ伝えるかはご家族でよく話し合っておくことが必要です。
また、菩提寺(お寺にお墓)がある方は、菩提寺との関係も非常に大切なポイントです。直葬を選ぶ場合でも、菩提寺があるご家庭では、後日あらためて本堂で読経をいただく「骨葬(こつそう)」を行うのが一般的です。たとえ事前に住職へ説明していても、骨葬を省略できるわけではありません。しかし、事前の相談によってトラブルを回避できたり、納骨がスムーズに進むなど、心の負担を軽減できる可能性があります。
そして忘れてはならないのが、「故人をどんなふうに送りたいか」という思いの部分です。宗教的な儀式を行わなくても、たとえば有料の部屋を1時間程度借りて、安置所でゆっくりとお別れの時間を持つことも可能です。火葬場にはこうした施設がないことが多いため、ご遺体を安置している施設で行うのが一般的です。
簡素であることが目的なのではなく、納得のいく別れ方をどう作るか。その視点を持つことが、後悔のない直葬のためにとても大切です。
✅まとめ:直葬は“手段”であって“答え”ではない
直葬は、時代の流れや価値観の変化に合わせて広がってきた、新しい葬送のかたちです。費用を抑えられ、準備の負担も軽いというメリットがある一方で、選び方や周囲との関係性、送り方の工夫によっては、思わぬ後悔につながることもあります。
ここでお伝えしたかったのは、直葬はあくまで“手段”であって、“答え”ではないということです。
「直葬が良いか悪いか」ではなく、「自分たちにとってどう送りたいか」を考えることが何より大切です。
葬儀には、亡くなった方を弔うという役割だけでなく、残された人が気持ちに整理をつけ、納得して前に進むという大切な側面もあります。形式にとらわれず、自分たちにとって意味のある形を選べるように、事前に知識を持ち、関係者とよく話し合っておくことが、後悔しない選択へとつながります。
🔶世田谷区で直葬をお考えの方へ
「本当にこれでいいのか」と迷われている方にも、火葬場や安置施設のご案内、菩提寺への配慮まで、地域に根ざした葬儀社として丁寧にサポートいたします。
シンプルでも、心のこもったお別れができるよう、ご家族の気持ちに寄り添いながらご相談をお受けしています。
世田谷区での直葬に関するご相談は、24時間遠慮なくお問い合わせください。

株式会社蒼礼社
代表取締役 塩田 正資
株式会社蒼礼社は、皆様の大切な想いに寄り添いながら、葬儀のご相談をお受けしています。 私自身14歳で父を失った経験から命の儚さを感じ、この仕事に携わるようになりました。 蒼礼社では、ご遺族が安心してお別れできるよう、全てのプランに「エンゼルメイク」を含め、 故人を穏やかな姿でお見送りいただけるよう、心を込めてサポートしています。
-

2025.05.12
安くて簡単”の裏にある落とし穴?直葬を選ぶ前に知っておきたい5つのポイント
-

2025.02.14
プロが教える!家族葬・1日葬で失敗しない喪主挨拶:実例と安心の準備ステップ
-

2025.01.24
家族葬の香典マナー完全ガイド 失敗しない5つのポイント
-

2024.12.04
返礼品について
-
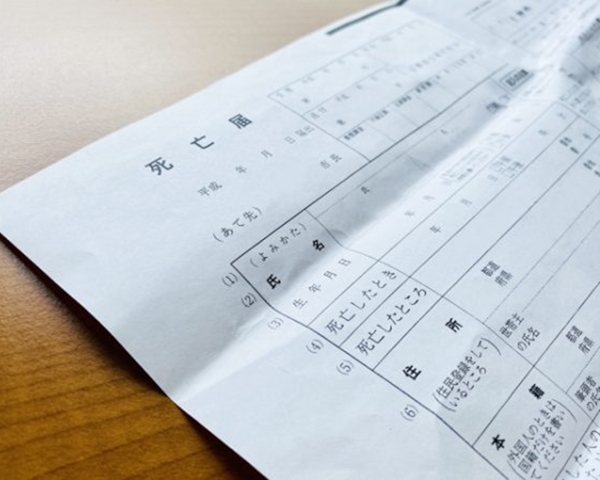
2024.11.05
死亡届のわかりやすい書き方と注意事項
-

2024.09.29
初めてでも安心!喪主の心得と葬儀の基本的な流れ
-

2024.09.01
初めての葬儀日程の決め方:押さえておきたいポイント
-
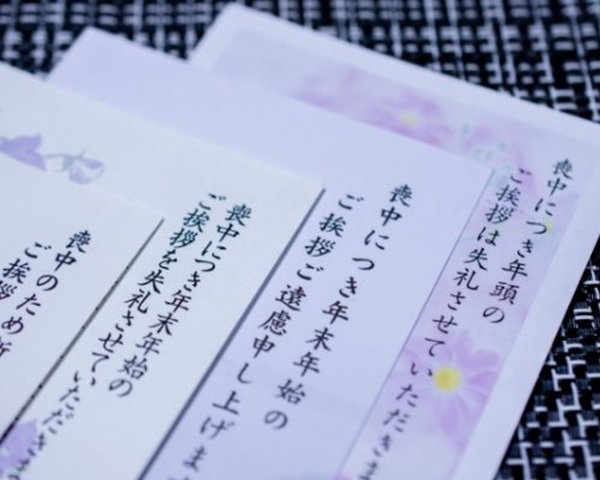
2024.06.13
忌中と喪中の違いとは?知っておきたい喪に服す期間とマナー
-

2024.03.13
お彼岸の意味と過ごし方
-

2024.01.29
忌引き休暇とは?制度の概要と意義を解説
式場案内 / 対応エリア
お問い合わせ
こちらからご相談ください。
また、供花の手配も承っております。
お気軽にお問い合わせください。

下記の地図にある左上のアイコン をクリックすると、表示される情報を変更できます。
をクリックすると、表示される情報を変更できます。
1都3県にある主要な火葬場、区営または市営の式場、寝台車、ご遺体を安置する施設が一目でわかります。